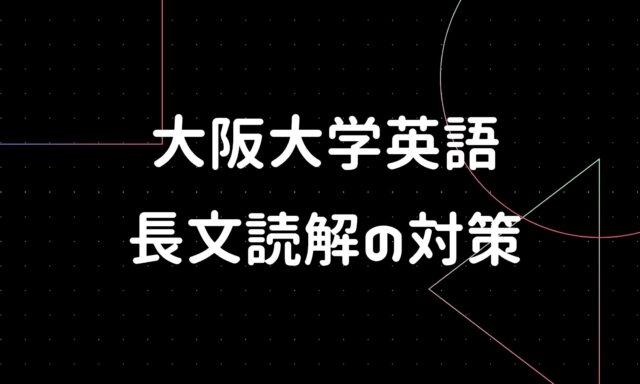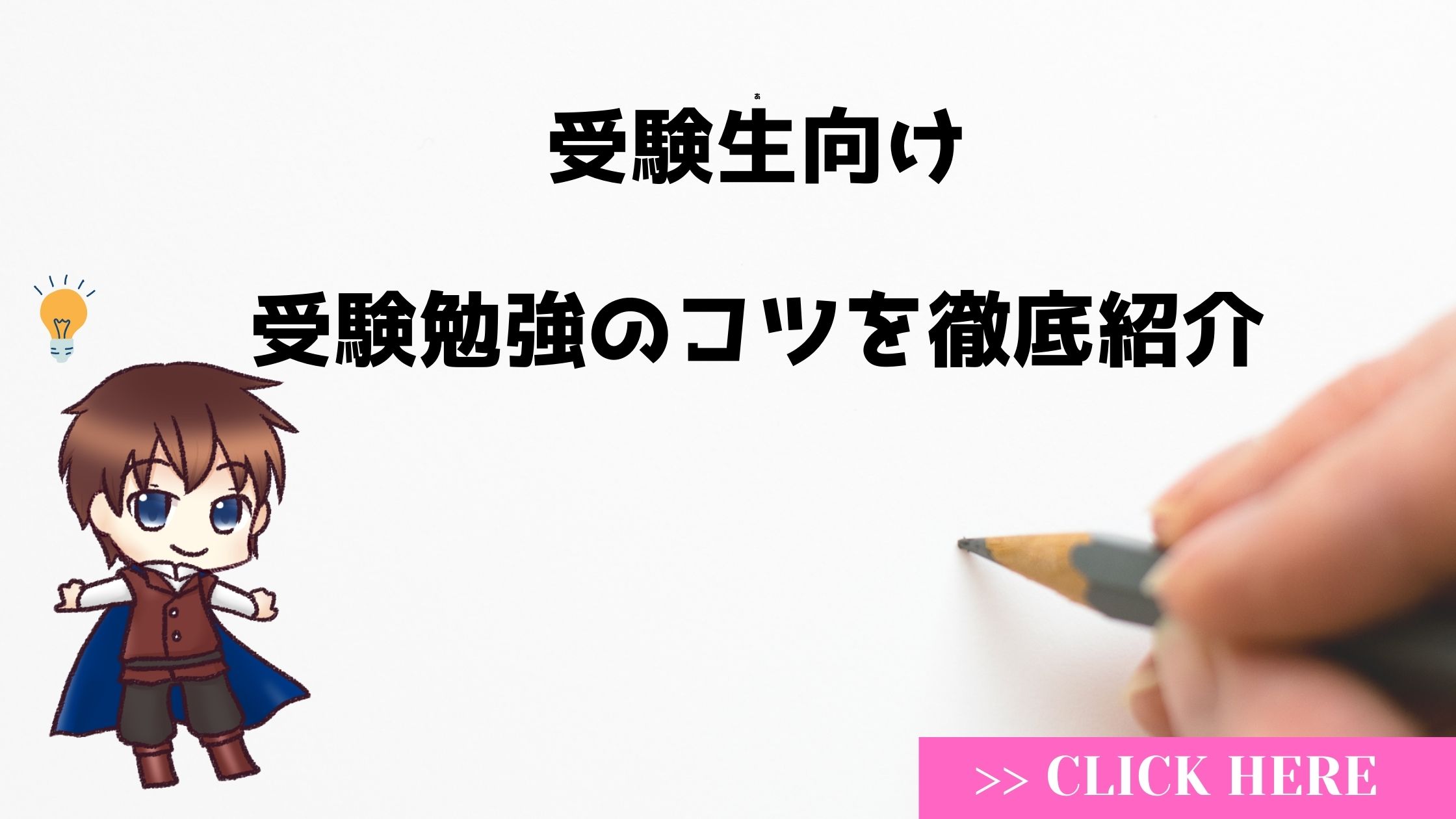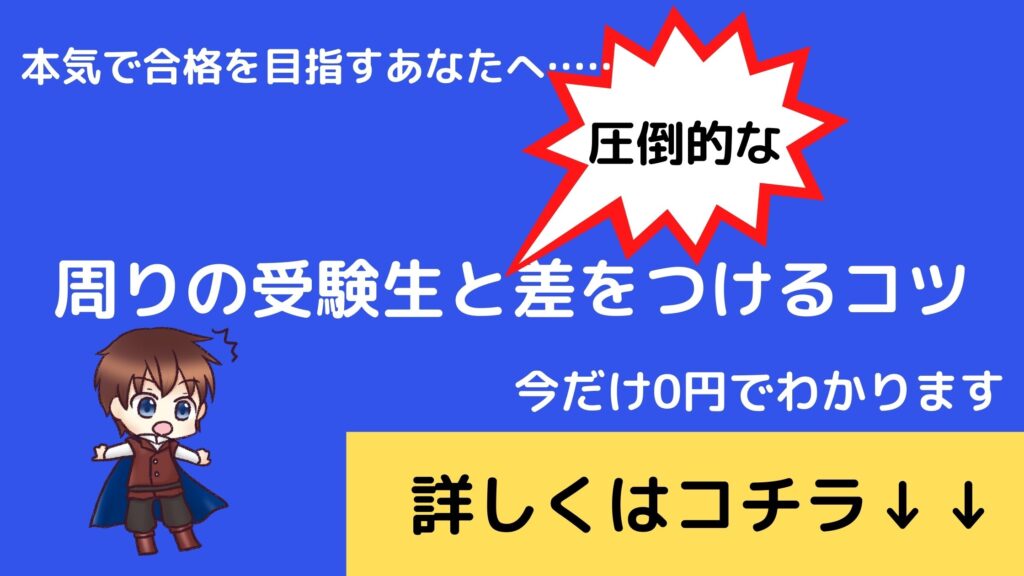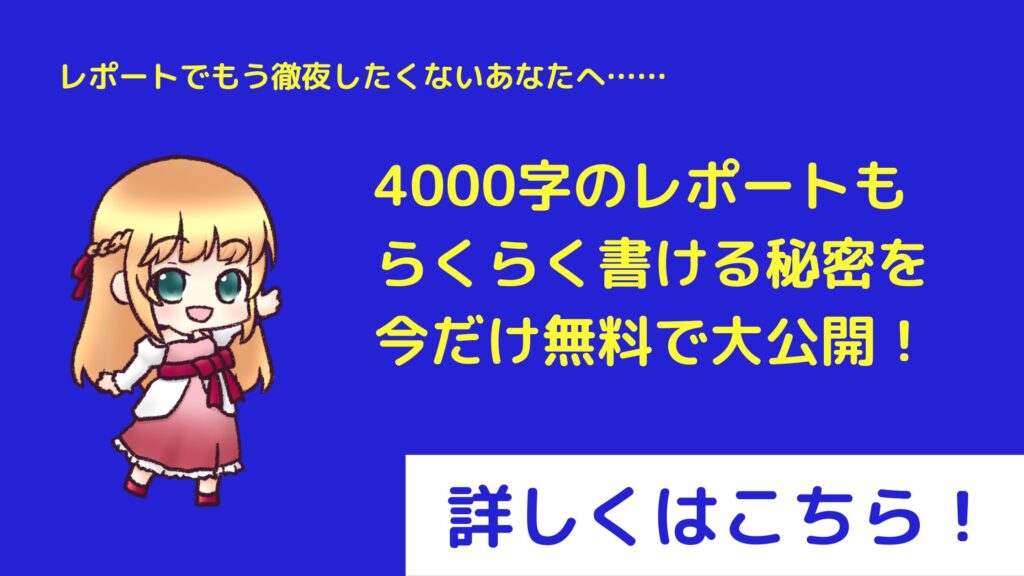阪大外語を受験するに当たって、核となる試験科目はもちろん英語です。
そんな2次試験の英語の中でもっとも分量が多いのが第2問の長文読解総合問題です。
阪大外語の入試独自の問題である長文読解の文章は難解できちんとした対策をして臨まなければいけません。
そんな鬼門ともいえる阪大外語の2次試験英語、第2問長文読解総合問題の対策を徹底的に解説します。
大阪大学外国語学部二次試験英語の長文読解

とにかく量が多い!
初めて問題を見たときはまず問題文の長さに驚くでしょう。問題文の長さは1000語を超えます。
時間的にも余裕があるわけではないので、いかに集中して読み、そして、その膨大な語数の英文を読み切るかが肝になります。
設問はすべて論述形式

設問はすべてが日本語で書き込む論述形式です。問題のタイプは以下の通りです。
下線部和訳
表しなさい、と書かれていますが、用はわかりやすく日本語で訳しなさいという意味です。通例2行から4行ほどの下線が引かれ、その部分を日本語に訳すよう求められます。
どのようなことか説明しなさい
説明問題です。文中から具体例や根拠を探し出し、それを記述します
なぜか、説明しなさい
問われている事柄の理由を説明して記述します
大阪大学外国語学部二次試験英語 長文読解の対策
阪大外語の英語の問題のなかでレベルを比べると、
読解 普通
時間 かなりかかる
設問 やや簡単
語彙 やや難しい
設問部の語彙 やや簡単
設問部の構文 やや難しい
と考えられます。
1000語の文章、と聞くとかなり難しそうな印象を受けますが、実は内容としてはそこまで難しくありません。
阪大が公開している出題の意図には、長文の中から答えを正確にさがし、それを簡潔に日本語でまとめること、とされています。
大阪大学ホームページ 「過去の入試問題・解答例等」より要約
ポイントは長い長い本文からピンポイントで答えを探し出す力をつける必要があるのです。
ここでは阪大が要求する力をつけるために、読解と解答の2段階に分けて対策を解説します。
読解編

1000語近い英文を読んだことがある方はどれくらいいるでしょうか。
共通テストでも1000語なんていう長文は見られません。何よりも、1000語という長文に慣れる必要があるのです。
本来ならここでおすすめの参考書は……となるところなのですが、私は見つけられませんでした。
理由としては
1000語を超える長文であり、難易度が高く、かつ解答形式がすべて日本語論述という問題集がないからです。
つまり、対策方法はただ一つ
阪大外語の過去問と実戦模試の問題集を解くことです。
しかし、ここにも注意点があります。阪大外語の長文が1000語を超えるようになったのは2011年か2012年(だったはず)のことです。つまり、勉強できる素材が非常に少ないということ。
前回の 【国公立2次対策】英語長文問題の勉強方法を徹底解説! レベルに合わせた勉強法がわかる! では音読学習をお勧めしました。
音読学習ももちろん大切ですが、初見の問題を本番と同じようなつもりで解くことも同じくらい大切なことです。
ある程度阪大外語の英文を読めるような下地をつくってから過去問に取り組むことが必須です。
解答編

先ほども説明した通り、旧帝大の英語の長文の中では、分量こそ多くても決して設問は難しくありません。
設問は下線部周辺をそのまま日本語に起こすだけで解答になってしまうことが非常に多いです。
阪大公式発表の意図にもあったように、目的の場所を正しく見つけ出して、日本語にまとめる必要があります。
ポイントは以下の通りです
設問部が近づくと語彙が簡単になる
解答に関わる部分は語彙が簡単になる
設問や解答に関係ない部分は難解な表現が多い
一概に言えるわけではありませんが、経験上このような傾向があります。これはいかに阪大側が必要な部分を効率的に探し出す力を求めているかがわかる傾向です。
初めて問題を解くと、語彙や表現にびっくりすることも多いと思います。
しかし、必要なのは全文章を把握する能力ではなく、必要な部分を日本語に直す能力です。それを念頭に置いて文章を読み進めてください。
大阪大学二次試験英語の長文読解対策は確実に!

いかがでしたでしょうか。1000語を超える長文と聞くと難しいとも思いがちですが、ポイントを絞って取り組めば、非常にシンプルな問題です。
語彙や表現の点では第1問の和訳問題のほうが難しいといえます。
ただ、この長文に慣れることは絶対に必要です。はやめはやめの対策を心がけましょう。